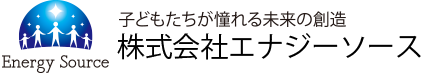ファシリテーション
先行き不透明な時代を突破するファシリテーション力とは!
VUCA時代において、様々な価値観を保有する人たちを取りまとめ、組織を目標実現へと導くことは容易ではありません。それぞれが異なるものの見方・考え方、価値観を持ち、その正当性を主張する人もいれば、意見を押し殺してしまう人もいます。
誰が正解を保有しているのかがわからないのです。これでは相互理解ではなく対立が生まれたり、声の大きい人のみの意見が採用されたりと、本来求めている状態から程遠い結果となってしまいます。
だからこそ今、個と組織にファシリテーション力が問われているのです。
ファシリテーションとは、目標実現のため、参加者の保有するものの見方・考え方、価値観を引き出し、課題解決をチームで促すことです。大切なポイントは参加者同士の相互支援の考え方です。
例えば、
こんなやり取りを聞いたことはありませんか?
「だったら会議の場で意見を述べたら?」「後から文句を言うなんて卑怯」という声が聞こえてきそうですが、その正論を述べる前に、組織のリーダーとして、見つめ直すところはないのでしょうか。
以下のチェックリストで「セルフチェック」を行ってみてください。

〜チェックリスト〜
上記項目に2つ以上「✔」が入る組織は要注意です。
生産性が高く、意義ある会議を進めていくためには、
- ゴールに向けて参加者の多種多様な発言を促進する。
- 議論を広げていき、大切なポイントを引き出しながら意見を整理する。
- 参加者の納得感を生み出すように議論を収束させ、合意形成へとサポートする。
と言ったような、会議を円滑に進めるファシリテーション能力の習得が必要不可欠となります。
ファシリテーション能力が磨かれることによるメリット
▶ムダな会議時間が激減する。
タイムスクリプトに沿った発言や進行をおこなうため、話がまとまらなかったり、横にそれたりすることを未然に防ぎます。気づいたら時間が大幅にオーバーしていたというようなことがなくなり、時間管理ができた会議を進めることが可能になります。
▶個々のモチベーションが向上する。
全員参画が基本ルールのため、個々の思いを表現する場が平等に与えられます。また、異なる価値観を否定するのではなく、理解しようとするため、組織への所属意識が芽生え、そのことがモチベーションにもつながっていきます。
▶一致団結力が高まる。
相互支援という考え方をベースに、共に一つの目標について考え、解決まで導くことをおこなうため、一体感がうまれます。一つの課題を解決するたびにチームの団結力が強化されていきます。
▶達成手順が明確になる。
次にどのようなアクションを起こすのかという「いつ」「誰が」「何を」「どうするのか」を明確にするため(可能であれば5W2Hにまで落とし込む)、参加者一人一人がなにをすべきかが明確になり、確実に行動へ移行されます。また、チェック機能をきちんと働かせるため、軌道修正も可能になります。